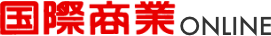オルビスは、生涯顧客づくりを強く意識している。人口減が進む日本では、新客依存のビジネスは成り立たず、顧客一人ひとりのLTV(Life Time Value・ライフタイムバリュー)を上げることが必要である。商品とコミュニケーションを軸にした体験価値の提供を通じて、ブランドと顧客の絆を深めなければいけないから、18年にオルビス社長に就いた小林琢磨氏はブランドビジネス強化を推し進めてきた。ただ、それは競合他社も同じ。ここでの差別化競争が激しい。そこでオルビスは創業35周年の今年、創業時から重きを置いているCRM(顧客関係管理)における事業計画の柱の一つである「アプリコアサービス事業」をもう一段階加速させる。その鍵となるのがオルビス独自のCDP(Customer Data Platform・カスタマーデータプラットフォーム)の進化だ。具体的には、顧客、購買、診断という三つのデータを組み合わせ、多様な顧客接点に適した体験価値を創出し続ける「アプリコアサービス事業戦略」。これが動き出すと、ブランド(オルビス)と顧客の関係性は、様変わりするのではないか。
オルビスは、18年から独自のCDP構築の準備を進めてきた。ブランドの体験価値を最適な形で消費者に伝えるために、アプリ中心のコミュケーション戦略を実行する。その手始めとして、チャネル別組織からチャネル横断組織への移行に踏み切った。それだけ、オルビスの組織の壁は高く、そして分厚く、三つのデータを結びつけるのは至難の業だったのだ。
リブランディング前のオルビスでは、チャネルの特性を優先し、店舗とカタログでは季節のプロモーション商品が異なることが多かった。例えば、店頭ではニキビケアのスキンケアを勧める一方で、カタログでは店舗とは別の施策で優良顧客向けのエイジングケア品を勧めるなど、チャネル特性が優先されてしまうケースがほとんどだったのだ。そうして、オルビスのLTVは伸び悩み、販促強化による新客獲得に頼らざるを得ない状況に陥っていた。
オルビスがリアルとECの連動を生むには、自主自立で成長してきたチャネル別組織の統合が必須。だから、通販事業、店舗事業というようなチャネル別組織だったが、マーケティングの機能別組織に移行した。2022年からは新たにCRM統括部の一部門下で統合し、本質的なOMOを行っている。店頭でのリアルなブランドからEC、アプリまでをシームレスな顧客体験を戦略的に実行する組織に進化し、オルビス流CDPの土台になるという。元木正城執行役員(CRM・メディア戦略管掌)は次のように説明する。
「長く続いたチャネル別組織を変えることは勇気がいることです。なにしろ、過去の成功体験を壊すことですから。ただ、きちんとブランド価値をお客さまに伝えるには避けては通れない改革なのです。組織改革で実際に社内では混乱が生じましたが、総力を挙げて18年にリニューアルした『オルビスユー』が大ヒット。ブランドビジネスへの転換に社員も手応えを感じられたことで組織改革は成功裏に終えることができたのです。じつは19年のコミュニケーションへの投資のうち、9割以上を『オルビスユー』を注ぎ込みました。この大胆な戦略を決断し、実行し、結果を残した組織ですから、次のステップである多様な顧客接点を生かしたCRM構築も必ず成功すると思っています」
オルビスのアプリコアサービス事業戦略は、AIを活用した診断系サービス拡大によるパーソナライズされたブランド体験を実現し、テクノロジーを活用したブランドの体験価値向上を目指すもの。一見すると、デジタルやECを重視し、リアルを軽視する戦略に思えるが、決してそうではない。ECと店舗の両方を利用するお客は、それぞれ片方のお客よりもLTVが高い。ECと店舗の買い回りを生み出すことは、オルビスにとって真の愛用者を生み出すことになる。つまり、オルビスは、ブランドと顧客が身近に接するアプリを中心に置きながら、あらゆる顧客接点の機能をより先鋭化させるとともに、シームレスな結びつきを生もうとしているのだ。それはオルビスが顧客接点それぞれに自信を持っていることを物語っている。
例えば、コールセンターには、オルビスのホスピタリティの真髄が詰まっている。電話注文に対応するスタッフ「ビスタ」からは、いくらEC浸透率やアプリのダウンロード数が増えても、10年、20年の付き合いの顧客は離れない。昨今のシニア層はコロナ渦によってデジタルに触れる機会も増えた。オルビスは、EC注文には距離を置いていても、LINEを使いこなしているVIPのシニア層顧客が多いことに着目。ビスタが顧客とLINEでつながる試みは、今では数万人規模のコミュニティに成長している。ビスタからの通知は開封率90%以上で、シニア層はLINEを介したブランドとの交流を使いこなしている。それでも電話注文が減らないのは、ビスタとの絆が深い証し。これがオルビスが大切にしている理想の姿だろう。
ビスタはもちろん、店頭のビューティーアドバイザー(BA)が培ってきた顧客との距離感、提案の頻度やタイミング、相談の乗り方や答え方などは、オルビスの無形の資産と言える。このノウハウは、アプリのUIや診断系コンテンツの開発にBAやビスタを巻き込むことで取り入れ、アプリのUI、売り場のMDは、オルビスらしさを失わず進化を続ける。それだけではなく、BAはトレーナーの役割も兼ねており、全国の売り場で働くBAへの水平展開もスムーズに進む。正確な肌診断のやり方を徹底することで、精度の高いデータが取得できる。これも独自のCDP構築に不可欠な要素というわけだ。
一方、BtoBの売り場も、オルビスの大事な顧客接点になっている。特に、21年に参入した化粧品専門店チャネルでは、ブランド価値を高める成果が生まれ始めている。22年7月現在、北海道、宮城、東京、愛知、岐阜、和歌山、広島、山口の化粧品専門店に売り場を設けている。とりわけ地方の場合、化粧品の買い場は集約化が進んでいる。オルビスは、著名なビューティーブランドが揃う化粧品専門店の売り場に什器を展開することで、自社の売り場(EC&直営店)では獲得できない化粧感度の高い顧客にアプローチしている。元木執行役員は次のように話す。
「BtoB事業ですから、詳細な顧客情報を得ることはできません。ただ、店舗のECへの貢献度や顧客数の増減を推計することはできる。ECとリアルそれぞれの新客増は間違いなく、ブランド価値の体験の場を増やすBtoB事業の役割は磨きが掛かっています」
日本の消費者は、狭小商圏が生んだ多様なチャネルを使い分けている。ただ、化粧品業界はチャネル別の売り場展開を長く続けてきたことから、日本の賢い消費者への対応に出遅れたとも言える。その点、オルビスは創業の原点である通販、ネット黎明期から取り組むEC、そして直営店とBtoB事業と多様な顧客接点を同時に育ててきた。これが自社内でシナジーを発揮するように組織を改め、いよいよ22年内に「アプリコアサービス事業戦略」の大幅アップデートに挑む予定だ。創業35周年を経て、オルビスの生涯顧客づくりは一段と加速する。