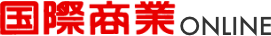化粧は華美・派手であってはならず、TPOに合ったものでなくてはいけません。けばけばしい化粧は避けるべきで、ベースメークもあまり濃く塗ると「石仏のようだ」と後ろ指を指されることに。自分の顔に似合うよう細やかに濃淡があって、自然に見えることこそ、好ましいお化粧なのです。
こう説いたのは、よそおいのみに内容をしぼった美容総合読本の最初期の刊行物と考えられている『都風俗化粧伝(みやこふうぞくけわいでん)』。江戸時代後期、文化10年(1813)刊行です。
江戸時代のメークは、基本的に白粉で行うベースメークに、黒(眉とお歯黒)、紅を使ったポイントメークで完成します。真っ白な白塗りに真っ赤な口紅と思いきや、白粉の塗り方については多くのページを割き、白粉の濃淡で素肌感や立体感を出すなど、素肌感のある「ナチュラルメーク」法を展開します。「すっぴん風」「ナチュ肌」などと表現して、ベースメークをメークの土台として重要視する点は現代と共通します。明治時代になっても、「遠目では色白に、近付くと素肌のように見える」「生まれつき色が白いような白さ」など、ベースメークでつくる素肌美の訴求が続きます。
明治時代、開国とともに日本にもたらされた、たくさんの文化のなかに、欧米の化粧品や化粧法がありました。白ではない色つきの白粉は、明治30年頃から化粧品製造の本に登場、明治30年代末の新聞には「肉色水白粉(にくいろみずおしろい)」というフランス製の商品の新聞広告が掲載されています。
明治40年(1907)に刊行された美容書『新化粧』には、女優の川上貞奴がヨーロッパで見てきた化粧法が紹介されています。白粉の色数の多さ、実際に手に付けてみて自分の肌に合った色を選ぶことの大切さの提案は、白一色でベースメークをしてきた日本人には、さぞかし新鮮だったことでしょう。明治40年代以降、「自然色白粉」「淡紅色(にくいろ)白粉」などの名前で、国産品もつぎつぎと発売されていきました。
ところで、色白粉はじめオークル系の商品が登場したあと、桃色、水色、緑、紫などの多色展開をしていきます。いわゆる「肌色」は一色のみ。さまざまな色を、季節や自分の素肌の状態によって、単色あるいは数色をまぜて、素肌感のある肌を演出していました。多色展開をした要因の一つには、照明の変化があったようです。
色白粉をぬった肌は血色がよく見え、特に夜用の化粧品として最適と考えられていました。当時の都市部の灯りは、ガス灯や電灯で、昼間の太陽光とは色合いがだいぶ違います。そこで肌を自然に見せるコントロールカラーが必要になったのでしょう。夜会などでは、会場の照明を確認して、白粉の色を選ぶべきといったメーク指南もありました。
どんな光の下でも、素肌感が大事。そんな女心をサポートしたのが、カラフルな色白粉だったのです。(富澤洋子・ポーラ文化研究所 研究員)
※クレジット記載のない図版は、すべてポーラ文化研究所提供
| 株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス ポーラ文化研究所 ポーラ文化研究所は、化粧を美しさの文化として捉え、学術的に探求することを目的として1976年に設立されました。以来、日本と西洋を中心に、古代から現代までの化粧文化に関わる資料の収集と調査研究を行い、ホームページや出版物、調査レポート、展覧会などのかたちで情報発信しています。 [ホームページ] |