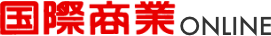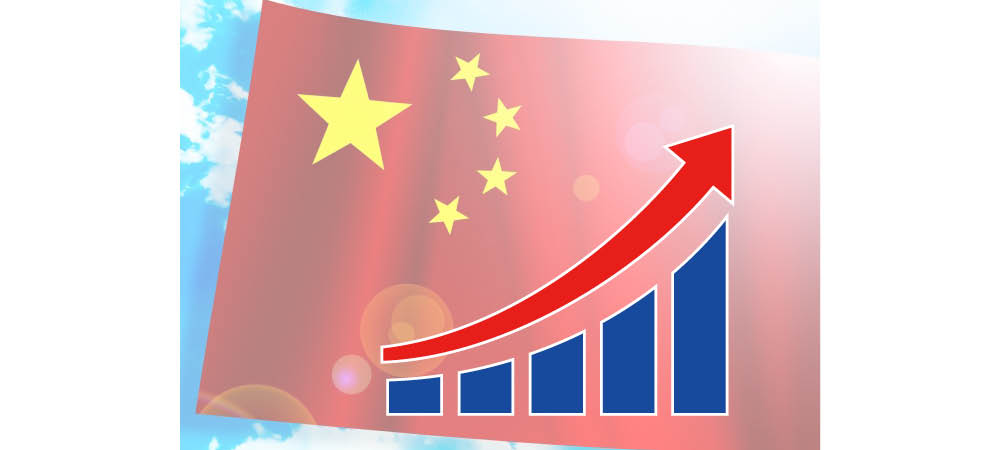日本とは打って変わって成長し続けるアジア市場。しかし、そのアジア市場も、右肩上がりの量的成長から、良い商品をしっかり吟味する質的成長に転換しつつある。いまこそ日本の「プレミアム」な製品を現地に投入し、違いのわかる消費者に訴求していきたい。そのような戦略を立てる企業は増えている。これまでは価格がどうしても合わずに参入を見合わせてきた企業も「プレミアム」というキーワードに背中を押されているのは間違いない。
確かに、アジア市場は、いままさに変曲点にある。例えば中国。一昔前、日系でいえばユニ・チャームやハニーズ。台湾系でいえばカップ麺大手の康師傅、岩塚製菓から技術供与を受けて成長した旺旺食品など、市場黎明期に低価格路線でマス市場を席巻した企業が成功者といわれてきた。しかし、いまとなってはいずれの企業も、高度化する消費者ニーズへの対応を迫られており、中国事業は収益面で難しい局面を迎えている。その意味で「プレミアム」を狙うのは正しい選択といえる。
しかし、そういった空気に水を差すようで申し訳ないが、正直なところ、「プレミアム」は若干の違和感を覚えることが多いキーワードでもある。なぜなら「プレミアム」戦略をとりたい、という担当者の多くが、肝心の「プレミアム」の定義と根拠について、明確に答えられない場合が多いからだ。
それだけでなく、現地スタッフ/本社スタッフ、商品開発/営業スタッフで見解が分かれることもある。笑い話だが、ある企業の社内でプレミアムの価格について聞いたところ、本社スタッフが最も高い価格を提示し、現場に近づけば近づくほど低い価格になっていく、ということがあった。「プレミアム」という言葉は「高く売りたい」という売り手の「妄想」になりがちなキーワードでもあるようだ。
売り手の「妄想」を「構想」に進化させる上で、「プレミアム」の定義と根拠を問い直すことは効果的である。例として、中国のビール市場を考えてみる。ここでも、市場の成長鈍化とともに成熟化が進み、「プレミアム市場」が立ち上がりつつあるということで、日系企業の取り組みが幾度となく国内メディアで取り上げられている(表1)。
直近でも、サッポロが、バドワイザーなどを擁する世界的ビール大手ABI(アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ベルギー)を販売代理店として、プレミアム市場に参入するとのリリースがあった。記事によれば、「高級ビールの需要は高い。サッポロも中国で売り出す商品の店頭価格は、330ミリリットル入りの瓶で約10元(約160円)を想定する。現地で標準的な価格は5元前後だが、サッポロは品質管理や醸造ノウハウなどの高さを訴求してブランドの浸透を図る」(日本経済新聞:18年9月19日)とのことだ。なかなか強気な価格設定に見えるが、実際にはどのようなポジショニングになるのだろうか。
このようなケースの検証には、実際に現場に足を運ぶのが一番である。試しに上海で調査した結果が表2だ(低/中/高/超高価格帯という分類は、チャネルを見た印象から設定している)。
この表を見てまず分かるのは、中国市場の価格帯の幅広さである。特に超高価格帯の部分については、近年アメリカなどへの留学から帰ってきた若者がクラフトビールを輸入販売するケースなどが増えており、急速に拡大している。一方、高価格帯というのはコロナやヒューガルデンなどの特色あるビールが揃っている。そして中価格帯では外資系メーカーの主要ブランドが戦っており、低価格帯では現地メーカーが中心という形だ。
このような状況において、サッポロの値付けである330ml・10元(500ml換算で約15元)というのは、実はそこまで強気ではなく、むしろ外資系の標準的な価格帯であることがわかる。
ただし、難しいのは、高価格帯と中価格帯、どちらに自社を位置づけるかが見え難い点だ。高価格帯と中価格帯では競合もチャネルも異なる。高価格帯に自社を位置づけた場合、エキゾチックでニッチなビールとして展開していくことになる。
一方、中価格帯に位置づけた場合、外資系や現地メーカーと正面衝突することになる。しかも、今回提携したABIは、どちらかというと中価格帯が得意な企業。これまでバドワイザーを使って現地メーカーと激しい価格競争をしてきた歴史がある。油断すると、中価格帯における価格競争に巻き込まれてしまう可能性があるわけだ。
仮にサッポロが価格競争に巻き込まれたくないと考えているならば、誰から見ても「プレミアム」であることが分かるような価格にするべきだったかもしれない。いずれにせよ、どうしても価格競争になりやすいビールという商材の特性を考えると、サッポロの値付けは、繊細な舵取りが求められるポジションにあるといえる。
このように「プレミアム」という言葉を一旦カッコに入れて、価格という具体的かつ現場に近いデータを元に考えると、自社の取るべき戦略や注意すべき点などを深く考える契機になる。社内で「『プレミアム』戦略で行こう」という話題になった場合には、このマジックワードに惑わされず、「現場現物」に戻る機会にするべきである。
著者:是枝邦洋(Corporate Directions, Inc. プリンシパル https://www.cdi-japan.co.jp)。