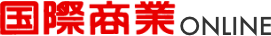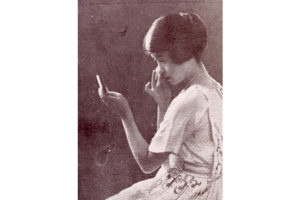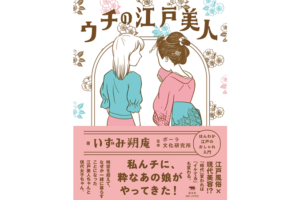ポーラ・オルビスホールディングスで化粧文化に関する研究活動を行うポーラ文化研究所は、2024年11月14日に東京国際フォーラムで開催された一般社団法人日本化粧品専門店協会が主催する「2024 CoReシンポジウム」で、「メンズ化粧の歴史をたどる 制度・美意識・化粧品」と題した講演を行った。
本シンポジウムでは「化粧品専門店におけるメンズ需要創出の仕掛け」をテーマとし、近年盛り上がりつつある男性の化粧品市場に焦点を当てた座談会を行った。その前段として、ポーラ文化研究所研究員の富澤洋子氏が登壇し、化粧文化研究の観点から歴史の中の男性化粧について講演を行った。

講演では、目的や役割を変えながらも、男性が化粧をしてきた証を縄文時代まで遡って紹介。埴輪(はにわ)に見る化粧の痕跡から、平家物語に残る公家と武家の化粧の違いにまつわるエピソード、戦国時代以降にみられる月代(さかやき。前頭から頭頂までを剃り上げた髪型)の所以などを、文献や絵画資料を交えて解説した。
また近代から平成にかけては、メンズ化粧品の流通が見られるもののアフターシェーブなど単品が主流だったことや、1980年代以降のYMOに代表される男性のメークの出現はありつつも、一過性に留まっていたことを指摘。このような過去と比較し、今ようやくボーダレス、ジェンダーレスの流れを受けて個人のマインドが変わり、「一般男性が化粧をすること」への社会の受け入れ態勢が整ってきたことを提言した。
聴講者からは、「埴輪や絵巻に化粧が表現されているとは思いもよらなかった」、「男性の化粧意識がまさか縄文まで遡るとは」といった驚きの声が寄せられた。