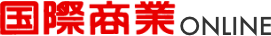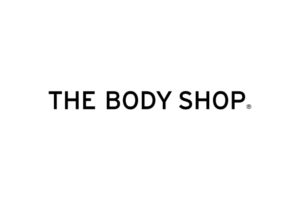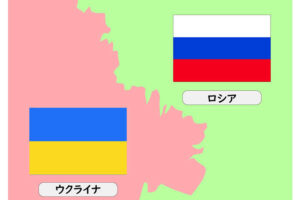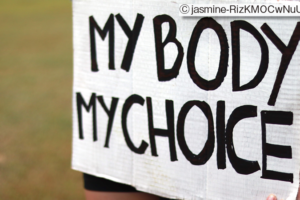近年「美しさに性別は関係ない」という「ジェンダーフリー」の考え方が、コスメ業界に大きな変化をもたらしてきた。かつては男性向け、女性向けとはっきり二分されて、髭剃り関連品や整髪剤は男性用、基礎化粧やメイクは女性用とアイテムも二元的な分類だったが、今やコスメは男女を問わず「自己表現の手段」として捉えられるようになってきた。
そして、今、欧米社会は、LGBTQ+コミュニティなどの影響を受け、「ジェンダーフリー」から「ジェンダーインクルーシブ」へと概念を深化させている。男女という二者択一の性別に基づく規範や制限から解放されるだけではなく、ノンバイナリーな性や人種、体形、年齢などあらゆる多様性を尊重し、人が個人として尊重され包摂されるべきだというものである。この社会的変化は、多様な人材を生かすことが競争力やイノベーションにつながると、ダイバーシティ(多様性)&インクルージョン(包摂)を経営戦略に組み込む企業が増え始めていることからもうかがえる。
コスメ業界におけるジェンダーインクルーシブは、特定の体形、肌の色、顔の形などを美の基準としていた伝統的な考え方を変容させ、個々の違いや多様性こそが美しさの一部であり、異なる外見や特徴が独自の美しさを持つという考え方を推進している。
本稿では、ジェンダーインクルーシブという新しい概念がどの化粧品カテゴリーに最も影響を与えているかを探るとともに、ジェンダーインクルーシブをコスメ業界に特化させた「インクルーシブビューティ」というアプローチにも触れてみたい。
化粧品カテゴリーの中で、ジェンダーインクルーシブの影響が大きいのは「スキンケア製品」だ。その背景には二つの特徴がある。まず男性用スキンケア市場の急成長だ。ロンドンに拠点を置き、リアルタイムでデータ分析やトレンド予測を行うリテイルとファッションの専門プラットフォーム「エディテッド(Edited)」が2023年9月末にリリースした資料によると、グローバルの男性向けスキンケア市場は23年末までに230億米ドル(約3兆2700億円)を超え、今後7年間は年平均で5.6%成長すると予測。世界広告研究センター(WARC)の最新調査でも、今では男性の56%以上が毎日スキンケアルーティンを行っていることが報告されている。
男性向けスキンケア市場の成長は、インフルエンサーが重要な役割を果たしている。例えば、アメリカの音楽プロデューサーであるファレル・ウィリアムスがスキンケアブランド「ヒューマンレース(Humanrace)」を、イギリスの4人組ボーイズグループ「ワン・ダイレクション」の設立メンバーで現在はソロで活躍するハリー・スタイルズがビューティブランド「プリージング(Pleasing)」をそれぞれ立ち上げている。製品デザインも、従来の黒、カーキ色といった男性向けイメージから抜け出し、清潔で自然なパッケージが好まれるようになっており、男性を対象にしたミニマルデザインは女性向け製品にも取り入れるようになっている。
二つ目の背景的特徴は、以前は弱点、あるいは隠すべきと考えられていた肌の特徴や違いを、むしろ美しいものとして価値を見出す傾向が強くなっていることだ。例えば、そばかすは日光によるものや遺伝的な特徴であるが、最近ではその人独自の美しさや個性を表現する要素として見なされるようになっている。老化現象によるシミやシワも、生きる上での自然な経過として肯定的に受け入れるべきだと考える。このような視点に立つと、スキンケア製品は、性別や年齢から連想する「美」を追求するものではなく、肌タイプや肌のトラブルに焦点を当てて、健康な肌を維持するために必要なアイテムとして位置づけられ、ターゲット層は全方向へと広がる。
従来の「美」から逸脱していても、それは弱点や隠すべきものではなく、むしろあなたを輝かせる美しいもの――。この考えは、「インクルーシブビューティ」という名のもとに、化粧品業界に新しい商品展開や、マーケティング戦略を迫っている。
例えばファンデーションに関しては、肌を明るく見せる色合いを基調に展開されることが一般的だったが、現在は多様な肌色、色調に適合するファンデーションが求められている。黒人の肌の場合、ベージュ色のバリエーションでは美しさを引き出せず、化粧品メーカーにとっては、濃い肌色の美しいトーンを引き出すファンデーションの開発が課題となっている。そんな中で、M・A・Cやボビイ ブラウン(BOBBI BROWN)などは40色以上の色合いを展開して支持を得ている。また、カリブ海のバルバドス出身のシンガーでインフルエンサーとして活躍するリアーナが展開するフェンティ・ビューティ(Fenty Beauty)は50色のカラー展開を実現。ブランド立ち上げ時に自身のソーシャルメディアで「スキンケアに性別があるって言った人、それウソだから」というメッセージを投稿したことも話題を呼んだ。
ジェンダーインクルーシブは、コスメ業界ではビジネスチャンスとして歓迎されている一方で、その考えが定着するまでには相当な時間がかかるのではないかと、ある記事を読んで気づかされた。その記事は、肌やシャンプーなどの製品説明でよく見る「ノーマル(normal)」という概念に着目したものだった。肌のタイプや髪質などによるアイテム分類でよく用いられる語彙で、日本語では一般的に「普通」と訳されるが、この言葉には、「正常」「標準」というニュアンスがある。つまり、スキンケア製品では、脂性や乾性の肌は「異常である」というニュアンスを生み、シャンプーでも「普通の髪用」を製品ラインの中心にすると、「硬いくせ毛」や「猫っ毛」は標準ではないという意味合いを持ってしまう。
これらの問題にいち早く気づいたユニリーバは、主要ブランドのダヴ(Dove)から「体形、サイズ、プロポーション、肌の色」に対する表現を禁止し、200以上の製品からノーマルという語彙を取り除くと発表した。同社のビューティ&パーソナルケア部門トップのサニー・ジェイン氏は、「ノーマルという語彙を製品やパッケージから削除しただけで問題が解決するわけではないが、前進するための重要な一歩である」と語る。イギリスの市場調査会社ミンテル(Mintel)も、「伝統的な美の概念はZ世代には通用しなくなっており、美は自分の欠点を受け入れ、個性として見なすこと」と述べている。
コスメ業界では長きにわたり、「美には一定の基準があり、それに合わないと弱点やコンプレックスとなり、その克服のために美容製品を求めるのが消費者の主たる購入動機」とされてきた。しわ取り、美白、白髪染め製品など、例を挙げればきりがない。無意識の差別や偏見は自覚することが難しく、取り除くことも容易ではない。だからこそ、美容業界が率先してインクルーシブビューティを伝えていくことは、誰もが美しく輝く世界を作る上で、とてつもなく大きな社会的使命があると言えそうだ。★
■水迫尚子
デンハーグ在住のフリーランス編集者・ライター。日系企業のグローバルサイトや統合報告書の制作を請け負いながら、オランダで唯一のフリーペーパー『mooi-mooi』を発行している。
月刊『国際商業』2024年03月号掲載
トップ画像著作者:pikisuperstar/出典:Freepik