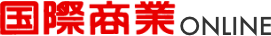ライオンの研究開発がドラスティックに変わるかもしれない。そのキーマンは濱逸夫会長だろう。2012年から社長を務め、19年1月に会長に就任。掬川正純新社長と二人三脚で、現場力強化による既存事業の成長と新しい成長エンジンの創出を両立。世界基準で競争できる企業への進化を図る考えだ。
18年11月の記者会見で、濱会長が強調したのは、スピード感の重要性である。いまや企業のグローバル競争に国・地域の壁は存在しない。「科学技術指標2018」(文部科学省科学技術・学術政策研究所)の企業部門の研究開発費を見ると、日本は09年に落ち込んだ後、漸増傾向が続いていたが、16年は対前年マイナス2・7%の13兆3000億円。それに対して米国は36兆5000億円、中国は35兆円。いつ、どこで、誰が新しい発想で、常識を覆す商品・サービスを生んでも不思議ではなく、ライオンが目指す世界基準で競争できる企業への進化は、これまで以上に容易ではなくなっている。この状況に従来の組織で、いま対応が難しくなっていることに、濱会長は強い危機感を持っているのだろう。
「社長の仕事は、トレードオフのものが多い。短期的な仕事に追われる一方で、中長期視点で仕込む仕事も進めなければいけない。短期的な仕事を積極的かつ集中してやりながら、成長エンジンをつくるという中長期のことも徹底的にやる。そういう体制でやらないと、本当の意味でのスピードは上がっていかない」(濱会長)
新体制への布石は、18年1月、研究開発本部内に「イノベーションラボ」を新設したことにさかのぼる。ライオンは2030年に向けた「次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーへ」を掲げ、以前から既存の領域から飛び出す新規事業の創出に取り組んでいるものの、濱会長が示す「複数の強力な成長エンジンの創出」には至っていない。
その背景には、120年以上前から日用品をつくり続ける老舗メーカーならではの重たい組織があるのかと思ったら、イノベーションラボの宇野大介所長は「外から見ると腰が重い会社に見えるでしょうが、当事者の我々からすると、イノベーションに向けて社内の機が熟してきたと感じている」と明かす。
その言葉は、12年以降の改革によって、組織の風土が一変したことを指す。経営と現場の距離が縮んだほか、営業部門・事業部門・研究部門の交流が明らかに増え、オーラルケアブランド「クリニカ」のリブランディグが成功するなど、高付加価値戦略が軌道に乗った。業績は右肩上がりに改善し、高利益を生むビジネス基盤が整った。研究開発本部長の乗竹史智執行役員は「研究開発本部のミッションは、イノベーションの源泉になること」と明言し、研究部門全体が同じ方向を向き続けている。さらに新規事業創出の必要性は、営業部門、事業部門の社員も共有。この組織の一体感は12年以降の改革で得た果実と言えるだろう。
「この状況の上に、イノベーションラボがある。オープンイノベーションの取り組みを誰からも反対されないのは、挑戦することへの土壌が整ったことを示していると思う。破壊的なイノベーションを起こすぞ、気を張って取り組んでも意味はない。徐々に画期的な商品、サービスが浸透し、5年後、10年後に気が付いたら生活が一変していることに気がつく。それができたら、かっこいいですよね」(宇野所長)
頼もしいぐらい、宇野所長が焦りを見せないのは、イノベーションラボの動きに手応えがあるからだ。メンバーの平均年齢は30歳代で、当初は研究員ばかりだったが、ダイバーシティを意識して、増員と入れ替えが進んでいる。
メンバーは日々の生活の中から、人々の困りごとを抽出。それを全メンバーと共有し、話し合いの場を設ける。喧々諤々の議論から、人々の困りごとの本質的な課題が見えてくると、イノベーションラボのテーマとして取り上げ、仕事が本格化する仕組み。細かいものも含めれば、三桁に近いアイデアが同時並行で動いており、その実現に向けては外部との連携も厭わない。「自由な発想を口にできる風土をつくらないといけない」と宇野所長は話す。
イノベーションラボの仕事は、社内外からの並々ならぬ期待はかけられていることを考えれば、決して楽ではないが、発足1年目の18年、目に見える実績は出している。新美容機器「VISOURIRE(ヴィスリール)」の開発に向け、国内最大級のクラウドファンディングサービス「Makuake(マクアケ)」を活用した開発・事業化プロジェクトを開始。瞬く間に目標金額の300万円を突破し、1000万円の大台もクリア。19年中に市場投入される予定だ。
また、ライオンが保有する口臭に関する知見を活用した口臭ケアサポートアプリ「Re PERO」を開発中。都内の小売業の接客スタッフが対象の実証実験を18年10月に実施した。しかし、宇野所長は「これら成功事例ではない。イノベーションラボのゴールは、永続的な事業を生むことだから」と指摘し、次のように話す。
「より期待される面もあるし、もっと速くできたのでは、との指摘もある。次のアイデアを出さなきゃいけないというプレッシャーもある。だからこそ、メンバーには、視野をもっと広げて欲しいし、それをさせるのが私の課題だ」
そもそも垂直統合で成長してきた日本企業は、オープンイノベーションに不慣れ。だからこそ、ライオンのイノベーションラボは、これから積み重ねるノウハウを組織に水平展開する役割も担うべきだろう。濱会長の狙いが、ここにあるとすれば、12年に始めた改革、イノベーションラボの新設、新体制の役割分担は、中長期どころか、超長期視点に立った戦略構築と言える。2020年代のライオンは、際立つ独自性を持つ企業に変貌するかもしれない。