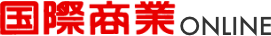マンダムのマーケティング改革が動き出した。その重責を担うのは、現社長の次男である西村健常務執行役員だ。業績を見ると、主力の男性事業だけでなく、近年は女性事業も成長しているが、2027年の創業100周年までに目指すのは「総合化粧品ではなく、唯一無二の強みを持った化粧品会社」で、ターゲットは「グローバル10億人」。マンダムは企業価値と商品価値をどのように生活者に伝えていくのか。西村健常務執行役員にマーケティング改革の方向性について話を聞いた。
国内用という思い込みを払拭できるか
--マンダムのマーケティングの特徴はなんでしょうか。
西村健(以下、西村) マンダムの「MANDOM PRINCIPLES」の一つに「生活者発・生活者着」とあるように、マーケティングの強みは、とことん生活者を見ていること。この考えは、ずっと持ち続けるべきものだと思います。ギャツビーは19歳を軸にプラスマイナス2歳、ビフェスタは20~30代を中心に働く女性、ルシードはミドル男性と、ブランドごとにターゲットは異なりますが、この分野であれば、世界中のどこのメーカーよりもマンダムが詳しいと自負できるかどうか。自分たちがナンバーワンだ、と言い切れるぐらいに生活者にコミットし、深く理解する。それを創業時から積み重ねてきたことが強みですし、今後はもっと意識して磨いていかないといけません。
--一方、課題については。
西村 グループシナジーを活かして競争することです。マンダムの海外事業は、1958年にフィリピン・マニラ市に技術提携会社を立ち上げたのが始まり。それ以降、積極的に各国に進出し、市場の奥深くまで入り込みましたが、そのぶん、各国の担当者が独自に市場を開拓する傾向が強い。一方、競合のグローバルブランドを見ると、幅広く各国生活者のニーズとウォンツを拾い、ブランド全体のコンセプトを築いている。その上で、各国の購買動向、流通環境などを考慮して、効率的なマーケティングを展開しています。これこそ、これからの時代に求められており、マンダムのマーケティングにも取り入れていきます。
--個別最適から全体最適へとシフトさせる、と。
西村 マンダムの海外拠点はアジア各国にありますが、現地から隣の拠点を見ると、意外と応用できる取り組みがあるんですよ。世界的に流行しているクラシックなヘアスタイルをベースに、サイドを刈り上げてトップを流す髪形「バーバースタイル」について、日本ではいち早く情報をキャッチしてギャツビーからグリースを発売し対応しましたが、アジアでは、まずインドネシアでブームが起き、ギャツビーのポマードがヒット。そして数年かけてタイ、ミャンマー、カンボジアなどに飛び火したのに加え、日本でもグリースをリニューアルしました。
各国の社員は日々の仕事に追われています。それにインドネシアの社員は、国内用に開発した商品だから、という思い込みもある。でも、インドネシアでヒットしているよ、ホットな話題だよ、と情報を各国に伝えれば、他の国の反応はもっと速かったかもしれません。さらにいうと、欧米の生活者が生むブームの兆しを察知するとか、すべての社員が世界中のトレンドに目を光らせれば、「バーバースタイル」の世界的なトレンドにもっとスピーディーに乗れたのではないか、と思っています。
--18年5月14日、グループのマーケティング機能を東京・青山に集約。目的は、グローバル規模でのトータルマーケティングの推進、国を越えた人事交流によるマーケティングノウハウの共有、グループでの新たな価値創造の三つですが、成果は出ていますか。
西村 大阪本社に男性ブランドチーム、東京青山に女性ブランドチームと分かれていたのを東京に集めましたが、明らかに組織の動き方、風土が変わり始めています。細かいことですが、これまで東京での仕事は出張しなければいけませんでしたが、その時間が省かれるだけでなく、商品開発チームとコミュニケーションチームの相互理解が深まっています。
例えば、コミュニケーションチームが担当するCM撮影の現場に商品企画のメンバーが立ち会うことが容易になり、新商品の使い方や見せ方などについて開発側の思いを伝えやすくなっています。逆に、開発チームは、15秒間のテレビCMの制作に対して、細部までこだわるコミュニケーションチームの姿を見るわけです。これはテレビ電話会議では生まれない、フェイストゥフェイスの連携だからこそ生まれる価値です。青山オフィスの稼働は、海外にも好影響を及ぼしているんですよ。
--どういうことですか。
西村 8月上旬、ギャツビーの国際会議を青山オフィスで行いました。これが3回目の開催で、前回までは大阪本社で開いていたから、青山オフィスに初めて来た海外スタッフがたくさんいました。青山や表参道の街並みはもちろん、社内の装飾もおしゃれで、みんなが新しいマーケの拠点に誇りを持ち、憧れの場所になったのは、大きな価値があると思います。
それから、国際会議では、主要テーマとして、ギャツビーの未来を語り合った。一人一人の思いが国境を越えてぶつかり合い、理解し合うことで、仲間意識が深まっていった。成長著しいアジア市場で勝てば、自ずと世界一が見えてくるじゃないかと、社員のモチベーションが高まっています。
これは日本の社員も含めてのことですが、社員の知的好奇心も広がっている。常日頃から私は、あらゆる瞬間に学びがあると考えています。洋服を選ぶときも、レストランを選ぶときも、読書の時間も、電車に乗っているときも、好奇心を持ってアンテナを張り巡らせていれば学びが得られますよ。青山オフィスを立ち上げることで、世界中の社員の視野が広がり始め、より感度の鋭いアンテナを張れるようになってきたと思います。
--大阪には管理部門と海外部門があります。本社の役割についてどう考えていますか。
西村 マンダムにとって創業の地ですから、聖地のような存在。会社の理念や文化を受け継ぐための象徴的な場所であることは間違いありません。管理部門や海外事業のヘッドクォーターは、東京になくても問題なく、本社を移転する理由にならない。それよりも、マンダムは、コミュニケーションにおいても、商品においても、昔から独特のやんちゃさ、ある種の“愛される図々しさ”があり、その根底には大阪の気質が流れていると感じています。本社を東京に移すと、短期間での変化はないでしょうが、長期的にはオリジンが見え難くなると思っています。
--東京を見ると、マーケティング部門は青山、営業部門は日本橋ですが、連携は生まれていますか。
西村 営業拠点が日本橋にあるのは、取引先へのアクセスが良いから。それにおかげさまで業容の拡大もあって、営業拠点も手狭になっており、マーケティング部隊を集約することはできません。それにマーケの役割を考えると、トレンドの発信地である青山、表参道界隈に社員が身を置くことに価値がある。メディアの方々との交流も取りやすく、それぞれの機能に適した場所に拠点があると思います。
場所は違えど、地下鉄を使えば、わずか30分で行き来できる距離ですから、定例会議はもちろん、一緒に小売店に足を運び、店頭環境に即した提案を考えたり、生活者のニーズ・ウォンツを拾ったり、様々な交流が取りやすくなっています。もちろん、これまでも営業部門から店頭の情報は上がってきていたものの、生活者のニーズ・ウォンツを見ながら、付加価値を生むマーケとエンドユーザーに届ける営業それぞれの強みを共有しながら、課題解決を進められるのは、とても価値がある。間違いなく、マーケと営業の連携は濃くなっています。
--青山オフィスに社員が有志で集まり、サッカーW杯を応援したり、ビフェスタの誕生日会を世界中のオフィスで同日開催したり、社内の情報交換が活発化。5月以降、インナーブランディングが進んでいるように感じています。
西村 社員は、オフィスを活用して、交流を深めてほしい。日本人は遠慮しがちですから、マーケや営業といった組織は気にせず、どんどん社員を巻き込んでいきたいです。まだ計画段階ですが、半期に1回程度、社員が集う企画をやるのも面白いのではないか。青山オフィスは、外部との交流を増やすことを大事にしていますが、社内行事にも活用することで、人と人のダイレクトなコミュニケーションの機会を増やしていきます。
マンダムの挑戦「②商品に比べ、経営や人材のグローバル化は進んでいない」に続く。