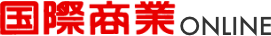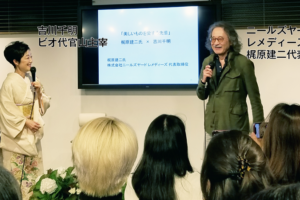期間限定無料公開(2025年3月19日15時まで)
※「キーマン」とは鍵を握る人物、組織などの重要人物、中心人物のこと。
ポーラ・オルビスHDは2025年1月1日付で、三つの主力事業会社の社長を交代した。不振が続くポーラは、オルビス社長として構造改革を断行した小林琢磨氏が務める。オルビス社長には、ディセンシアのリブランディングを指揮した山口裕絵氏が着任。そしてディセンシア社長には、オルビスの商品開発を支えた取締役の西野英美氏が就いた。3人の新社長は、それぞれどのように事業会社の競争力を磨くのか。忌憚なく話を聞いた。
ポーラ小林琢磨社長
顧客解像度を高めて体験を最適化する
――ポーラの強みは何でしょうか。
小林 ポーラは独自価値を“Science. Art. Love.”と定義していますが、私はうまく表現していると思っています。“Science.”が示すのは、最先端の研究を続けるポーラ化成工業と連携した商品開発。2025年1月1日の発売からわずか5日間で、全顔用先行美容液「リンクルショット メディカル セラム デュオ」が約1万個も売れるなど、相変わらずポーラの商品はお客さまからの支持が厚い。また、“Art.”を掲げているように芸術への造詣も深く、容器のデザイン一つとっても独自性がある。商品力と相まって、プレステージブランドの地位向上に一役買っているのは間違いありません。そして“Love.”。人と人の関係を大切にしたり、地域社会への貢献に人が介在したり、常に人に寄り添い続けることを大切にする哲学は、大きな強みだと思います。例えば、訪問販売が原点のトータルビューティー事業は、委託販売契約を結んでいるビューティーディレクター(BD)と強い絆があります。BD数は約1万9000人(24年12月末時点)で、競合他社が今から投資をしても、絶対にこれほど強いロイヤルティーを持つ組織はつくれません。ですから、客観的に見た時に、改めてリアル体験でお客さまとの関係を築いてきたポーラのアセットは強いと思っています。
――しかし、長らく委託販売の減収が続いています。その要因は何でしょうか。
小林 トータルビューティー事業は、店舗数と顧客数が完全な相関関係にあります。コロナの外出自粛によりBDは身動きが取れなくなったこと。さらにBDの高齢化が進み、辞める人が増加。その結果として店舗数が減り、売り上げが下がっています。BDとお客さまの強い信頼関係がポーラの強みですが、BDが辞めると顧客離れが起こる課題が露呈しています。ですから、ポーラの強みを最大限活用し、解決を図ります。
――具体的には。
小林 リアルのブランド体験の提供で強い顧客基盤を築き、LTV(顧客生涯価値)も高かったため、データドリブンのマーケティングに力を入れる理由が少なかった。ですから、顧客の解像度が低いままと言わざるを得ない状況です。例えば、生活者の購買行動は多様化していますから、ポーラの愛用者も複数の売り場を使い分けています。初めて買ったのはトータルビューティー事業の店舗でも、次は百貨店、その次はECで買っている可能性がある。しかし、これまでのポーラの仕組みでは、購買行動を分析しきれなかったため、店舗も百貨店もECも新客の扱いになり、2回目の来店を促す情報提供をしていました。実際は、ポーラを3回購入しているのですから、再来店とは違う情報を届けるべきでしょう。現在は23年4月に導入したメンバーシッププログラム「ポーラ プレミアム パス(POLA Premium Pass)」により、チャネルの壁を越えて購買行動を一元化していますから、CRMの改善がきめ細かく行えます。オンライン、オフラインを問わず、お客さまに適したポーラのブランド体験を提供できるように動きます。
――ポーラ復活は喫緊の課題。改革にはスピード感が求められています。
小林 オルビス社長には18年1月に就き、構造改革に挑みました。例えば、競争のポジションを変えたことです。当時のオルビスは通販化粧品ブランドという位置付けで、化粧品の売れ行きに大きな影響を持つ美容雑誌のベスコスに選ばれることはありませんでした。そこからリブランディングを行い、化粧品ブランドとして認知を確立し、23年頃からベスコスを受賞するようになりました。その間、コーポレートロゴやビジュアルアイデンティティーの変更など、抜本的にブランドを見直したのですが、それには社員との対話、組織風土の醸成などに多くの時間を割きました。しかし、ポーラの場合は、冒頭でお話ししたように、独自価値の定義があり、しかも認知度の高いブランド、商品がそろっており、改革はマーケティング戦略の強化から始められます。ですから、オルビスの構造改革よりスピーディーに目に見える成果を出せると確信しています。