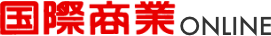「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。略して、薬機法と呼ばれるこの法律ほど、美容・健康業界の関係者を悩ませている法律はあるまい。そもそも、名称が示す通りもともとは医薬品に関するルールを定めたものであるが、法律の枠内にいる化粧品や医薬部外品の在り方を限定し、さらに法律の枠外にいる食品の表示にまで幅広く影響を及ぼしている。特にサプリメントに関しては歴史的にも「鬼門」といえる存在だ。医薬品という「聖域」が設けられ、それに近づくものには、時に「偽医薬品」として、逮捕、刑事罰を含む、厳しい制裁が加わるという建付けになっているからだ。薬や薬機法の歴史を踏まえ、美容や健康産業など、外からの視点も加味しながら、その在り方を検討していく。
薬は人間が生きる上で有益かつ効果的なアイテムであろう。病気を治し、進行を抑え、身体の苦痛を取り除く。日本では国民皆保険の恩恵で、これが安価に入手できる。ある年代以上のシニア層では、敬意を表す「御」という言葉をつけて、医薬品を「お薬」と呼んでいる。このことに、医薬品の効果への感謝と畏敬の心情が表れているとも言えようか。
実際、人と薬の歴史は古い。世界4大文明には既に薬の歴史が体系的に刻まれている。メソポタミアでは紀元前2000年頃に700種類の薬の調合法などが、粘土の板に記されていた。エジプトでもパピルスという紙の原型に同様の記録があるという。中国では、後漢の頃、西暦25年から100年超をかけて漢方薬の解説書「神農本草経」が成立した。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。