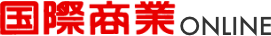花王ヒューマンヘルスケア研究所と国立研究開発法人理化学研究所(以下、理研)脳神経科学研究センター 知覚神経回路機構研究チームは、蚊に最適化した仮想空間装置を用いた実験により、CO2の存在が蚊の行動に影響を与え、さまざまな視覚情報やにおいに対する反応を強める可能性を明らかにした。この結果は、蚊に刺されやすい状況を理解する手助けとなり、効果的な対策を考えるための重要な情報になると期待される。
今回の成果は、2025年8月20日にNature Researchの電子ジャーナルScientific Reportsに掲載された(Kato-Namba A., Ohta K., Nakagawa T., Kazama H., Context-dependent effects of carbon dioxide on cross-modal integration during mosquito flight. Scientific Reports, DOI:10.1038/s41598-025-13427-z)。
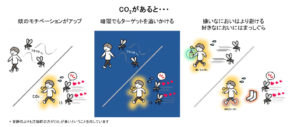
蚊は、感覚刺激を正確に受け取るシステムを備えており、ヒトの呼気中のCO2を感知して飛行行動を活性化し、視覚と嗅覚を頼りに近づき、熱と水分を検知して肌に降り立つ、というように、複数の感覚を順番に使って遠くのヒトにたどり着く。花王と理研は、仮想空間装置を用いて蚊の行動について研究を行っており、今回は、蚊が最初にヒトを感知するきっかけとなる感覚刺激であるCO2が、視覚や嗅覚にどのような影響を及ぼしているかを調べる実験を行った。これにより、三つの結果が得られた。
①CO2があると、動くものを追いかけるモチベーションが上がる
蚊を仮想空間装置に入れ、ヒトに見立てた1本の黒い線を見せ、蚊の動きに合わせて線を動かした。蚊は黒色に反応するため、線が動くと追いかけるが、CO2を嗅がせると、その追跡行動がより正確になった。
これまでCO2は、遠く離れたヒトを感知するきっかけとして作用し、その後、蚊は視覚情報を頼りにヒトに近づくと考えられてきた。しかし、実際の環境では、蚊はヒトを目視で捉えた後もCO2を感知し続け、CO2によってモチベーションを高く保ちながらヒトを追いかけていると考えられる。
②CO2があると、速く動くもの・見えにくいものも追いかけられる
次に、仮想空間装置の中で動く縞模様を蚊に見せた。通常だと、模様の動きを速くしても、蚊は一定のスピードでしか追いかけない。しかし、CO2を嗅がせると、速く動く縞模様でも追跡行動をとるようになった。さらに、本来は蚊にとって見えづらく、あまり追いかけることのない低いコントラスト(明度)の縞模様でも、CO2を嗅ぐことで追跡できることを確認した。
このことから、CO2が存在することで、蚊は視覚刺激に対してより感度よく反応できるようになると考えられる。
③CO2があると、好きなにおいにはまっしぐら、嫌いなにおいはより避ける
仮想空間装置の中で、蚊の好むヒトの靴下のにおいを嗅がせると、蚊はにおいのある方向に向かって飛ぶ。同じ状況でCO2を与えると、よりにおいに向かって飛ぶようになった。一方で、ハーブなどに含まれ、蚊が忌避する香り成分であるリナロールの場合、CO2があることでリナロールをより回避して飛行した。
以上の結果から、CO2は蚊のにおい刺激に対する好き嫌いも増強させる可能性がある。
今回の研究から、CO2の存在が蚊の行動に重要な影響を与え、さまざまな視覚情報やにおいに対する反応を強めることがわかった。CO2は、蚊がヒトを追いかける行動を強化する一方で、蚊が嫌な状況を避ける行動も強化する可能性が示された。例えば、薄暗い夕暮れ時にヒトを刺す蚊だが、CO2があることで本来なら見えにくいヒトでも追いやすくなっているのかもしれない。これらの発見は、蚊に刺されやすい状況を理解する手助けとなり、効果的な対策を考えるための重要な情報になると期待される。
花王 ヒューマンヘルスケア研究所の難波綾研究員は以下のようにコメントした。
「今回の研究で得た知見を活用することで、蚊をより効果的に誘引または忌避するための新しい素材や素材同士の組み合わせを見いだす可能性が広がります。そうした可能性の広がりが、蚊刺されによる健康被害を減らし、『未来のいのちを守る』につながると信じています。今後もさらに研究を進め、蚊の行動原理を深く理解していきたいと考えます」
また、理化学研究所 脳神経科学研究センター 知覚神経回路機構研究チームの風間北斗チームディレクターは、以下のようにコメントした。
「蚊のための仮想空間装置を構築したことで、CO2、視覚情報、においなどの感覚刺激を正確にかつさまざまな組み合わせで提示することが可能となり、蚊の行動の新たな側面を見いだすことができました。仮想空間を用いた実験には、蚊の行動を高時空間分解能で観察できたり、将来的には神経活動の同時計測と結び付けられたりする利点もあるため、今後も大いに活用していきたいと考えています」
月刊『国際商業』2025年10月号掲載