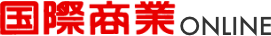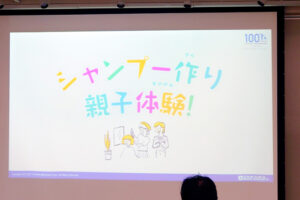タカラベルモントは、大阪大学大学院歯学研究科 再生歯科補綴学講座の高岡亮太助教、山本梨絵先生、西村正宏教授、および、ツインデンタルクリニックと「肥満と咀嚼関連パラメータの関係性」について共同研究を行った。肥満につながるとされる「速食い」は、これまで具体的な定義や客観的な指標が確立されていなかったが、単に咀嚼回数が少なく食べる時間が短いことではなく、一口が大きいことにより、咀嚼回数と咀嚼時間が減少し肥満に影響する可能性を確認した。この研究結果は、肥満防止のためのアプローチの開発につながる。

一口の大きさと肥満の関係のイメージ
なお、同研究結果については、2025年6月25日~28日にスペイン・バルセロナで開催された第103回国際歯科研究学会(International Association for Dental Research;IADR)にてポスター発表を行った。

IADRにてポスター発表した大阪大学大学院歯学研究科 再生歯科補綴学講座 山本梨絵先生
世界の肥満人口は増加傾向にあり、医学誌「The Lancet」で昨年発表された分析結果によると、22年時点で10億人以上が肥満とされている。また、昨年の厚生労働省の発表によれば、日本の20歳以上の肥満の割合は男性で31.7%、女性で21.0%となっている。メタボリックシンドロームや脂質異常症、高血圧といった生活習慣病の主な原因は肥満と考えられており、肥満改善は生活習慣病予防に貢献することが期待される。こうした背景から、肥満と咀嚼の関係性についてはこれまでさまざまな臨床研究が行われ、いわゆる「速食い」と肥満は関連することが明らかになっている。しかし、速食いについて定量化して評価したものはなく、速食いを改善するための食事指導は十分に確立されていない。
そこで、高岡助教らの研究チームは、肥満に影響を与える速食いを定量化し、肥満予防や改善のための食事指導につなげるため、研究に着手した。同研究では、タカラベルモント、ツインデンタルクリニックの協力のもと、測定を実施した。
被験者は23~88歳の健常な成人202名で、うち男性が123名、女性が79名。ただし専門的な食事指導やダイエットプログラムを受けている者を除く。
はじめに、質問票を用いて直近1か月の食習慣、ならびに自己申告による食べる速さを回答してもらい、体組成計で体重、BMI、内臓脂肪レベル、体脂肪率を測定した。その後、サンドイッチ2切れとおにぎり1個を食べる際の咬筋の筋電図を記録するとともに、動画撮影を行い何口で食べたかを記録し、食後の満腹度を10段階で調査した。記録をもとに総咀嚼回数、総咀嚼時間、何口で食べたか(総口数)、一口あたりの咀嚼回数、1分間に何口食べたか、1分間の咀嚼回数を算出し、統計解析を行った。
研究結果によると、総咀嚼回数、総咀嚼時間、総口数の3項目に関して、BMI、内臓脂肪(VF)レベルとの弱い正の相関が認められた。さらに、総口数については、BMI25以上の肥満群と25未満の標準群の2群間において、および、VFレベル9.6以上のVF過剰群と9.6未満のVF標準群の2群間において、有意な関連が認められた。
この結果より、総口数が最も肥満や内臓脂肪レベルに関与する可能性が示された。つまり、一口の大きさが大きいことが、肥満に影響を与える速食いであるという可能性が明らかになった。
今後は一口当たりの量をコントロールし、一口の大きさを小さくするような食事指導を開発することで、肥満予防や改善につながることが期待される。
月刊『国際商業』2025年10月号掲載