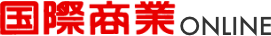最近ビューティー製品のラベルに、「ウォーターレス」という言葉を見かけるようになった。肌の手入れといえば、まずきれいな水をふんだんに使って顔を洗うことからというのが定番ではないだろうか。調べてみると、「ウォーターレス」(水を使わない)とは洗顔をしない美容法ではなく、「水を混ぜずに作った製品」を意味していた。
化粧品に含まれる水には、有効成分を溶かして肌に浸透しやすくする、ボリュームを増やして利益率を高くするなどの意味がある。しかし、水はそのままでは菌が繁殖して品質を劣化させることもあるため、保存料や防腐剤などの添加物も加えなくてはいけない。ヘルシーおよびエコ志向が強い人たちの間では、飲食物から皮膚につけるものまで「人工的に生成された添加物」をできるだけ避けよう、という傾向が顕著に強くなっている。添加物が少ないか全く使われていないウォーターレス製品はこうした層に訴求力が高い。シャンプーからスキンケアまで、水を加えた普通のものよりもずっと高価だが、日常的にオーガニック食品を購入するような平均より収入の高い中流層には、十分受け入れられるようだ。
またウォーターレス製品を作っているのは、廃棄ゼロ、プラスチックフリーを心がけるというエコなメーカーばかりだ。企業のエシカル/エコ経営度を査定する「Bコープ」認証を受け、そのロゴを商品に付けるブランドも多い。こういうところでは、製造過程においても節水対策を重視する。加えて、サステナビリティに対する企業としての態度を、優先的に評価して購入を決めることの多いZ世代も歓迎している。安くて環境に悪い商品をたくさん買うより、高くても自分の信条に合う良い品を一つだけ買う方がエシカルだと考える世代だ。こうして中流層とエコに敏感なZ世代をターゲットに、粒状の歯磨き、水を使わずに洗髪できるドライシャンプー、固形シャンプーなど単発のウォーターレストレンドがしばらく前から欧米の両方で起こっていたが、市場での存在感は日増しに大きくなっている。
製品自体には極力水を含めずに、使用時に少量の水か化粧水に溶かして使う固形スキンケア製品というコンセプトはもともと韓国が発祥だそうだ。しかし環境にいいからという理由で開発されたものではなかった。西洋ではこれが、水という貴重な資源をできるだけ無駄にせずに美容とウェルビーイングをケアする新商品アイデアを触発した、といえそうだ。
イングランド郊外でナチュラルスキンケアブランドとして起業した「イブ・オブ・セントアグネス」は、ウォーターレス製品「ビューティーキューブス」(https://beautykubes.co.uk/)を2018年に開発した。水を使わずに作ったキューブ状のスキンケア製品は、まずソーシャルメディア・ユーザーの間で話題になった。ブランド自体はアカウントも持たず、SNSでの口コミのみに任せたマーケティングはかえって好感を持たれ、いまではスキンケアとヘア、ボディまでカバーし12種類ほどの品ぞろえを持つ。自社ECもあるが、取り扱い店を見ると「廃棄ゼロブティック」のように環境意識の高さが感じられる店名が並ぶ。ウォーターレス製品ブランドにはこのような、中小サイズのスタートアップ企業が多いのが特徴だ。
もちろん、環境によいだけでは幅広い愛用者をつかむことは難しい。水だけでなく動物由来の素材もいっさい使わないスキンケア製品の英国ブランド「サブトラクト」(https://sbtrct.co.uk/)は、濃縮された植物エキスを配合し、ビタミン補給や保湿、アンチエイジングなどへの高い効果をうたっている。植物の抽出液を使った美容液もあるが、こちらも水は無添加とみなされ「ウォーターレス」だ。
調査会社インダストリー・リサーチによると、22年におけるウォーターレス・スキンケア製品のグローバルな市場規模は112億ドル(約1兆6600億円)で、28年には200億ドル(約3兆円)以上に成長すると見られている。多国籍大手ではこの動きに沿ってシュワルツコフがドライシャンプー、ガルニエはせっけん型の固形シャンプーなどを発売している。しかし、水も添加物も全く使わずに大衆向け価格の製品を作ることは容易ではないようだ。ユニリーバではすすぐ時に使う水の量が少なくて済むシャンプーやリンスを一度は発売したが、ポートフォリオから外し、むしろ、企業ポリシーとして、すべての商品作りに節水やプラごみ削減への努力をするというアピールに力を入れている。少量生産で価格も高いウォーターレス製品は知名度こそメインストリームになったとはいえ、ここしばらくは「エコなラグジュアリー」商品というカテゴリーに置かれそうだ。★
■冨久岡ナヲ
ロンドン在住ジャーナリスト。英国の動向を伝える記事を各種メディアに執筆中。今までに300名を超える企業エグゼクティブ、起業家、政治家、科学者などへの英語/日本語インタビューを行ってきた。英国企業や政府諸庁の日本語媒体制作、日本企業向けに広報素材の英語ローカライゼーション支援も手がける。
月刊『国際商業』2024年04月号掲載