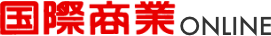スーパーの衛生用品コーナーで、日本では見たことのない青地に「亀」が描かれたマークの付いた製品を見かけた。よく見ると、亀は海面に浮いた白い布片の下でぐったり死にそうに見える。すぐ横にある「トイレに流すな」を示す赤地のマークと対になっていて目を引いた。赤地と青地のイラストの下には、「Plastic in Product(プラスチックを含む製品)」とアルファベットで書かれている。欧州でも、「死にそうな亀」を描いたようなネガティブなマークが商品についていることは珍しい。
これは欧州連合(EU)加盟国で販売される特定カテゴリーの製品に付けることになっている共通のマークで、筆者が見たのはウェットティッシュについていたものだ。2019年6月の「特定プラスチック製品の環境負荷低減に関わる指令」(通称「使い捨てプラ指令」Directive〈EU〉2019/904)は、プラスチック皿やカトラリーなどの使い捨てプラスチック(以降プラと表記)を禁止するものとして、日本でもある程度知られている。経済活動のループを閉じて循環化するために、使い捨てプラをできる限り禁止し、削減できないプラはリユースとリサイクルを推進し、環境汚染を抜本的に減少させることを目的としている。同指令には「浜辺で見つかるゴミの80〜85%はプラ製で、その半分が使い捨てプラ製品」とあり、浜辺でのポイ投げなどによってたどり着くプラごみが海洋汚染の大きな問題となっていることを指摘している。同指令で禁止されることになったのは、綿棒の軸、皿、カトラリーなど約10の製品カテゴリー。特に海岸でよく見つかる飲料用ペットボトルなどについては、加盟各国で国内法によって適切な方法を定めることとされている。
欧州委員会は、その後、この実施規則(〈EU〉2020/2151)を交付し、21年7月から、一部の使い捨てプラ製品そのもの、あるいはその包装に、亀のイラストを用いた「Plastic in Product」ロゴマークをつけることを義務付けた。対象となる製品カテゴリーは、①生理用ナプキンとタンポン②ウェットタオル、ウェットティッシュ③フィルター付きタバコ④プラスチックカップ(製品に直にロゴをつける)――で、図柄は対象製品が分かるように描かれている以外は、パターンとしては同じだ。例えば、生理用ナプキンとウェットティッシュでは、トイレに投げ込まれようとしているものや、海面に浮いているように見えるものは小さな布片のような形のもので、タンポンやフィルター付きタバコは見てそれと分かるイラストとなっている。欧州において、海亀は海洋プラ汚染の犠牲となる代表的な動物としてよく知られている。海中に浮かぶプラ袋をクラゲと間違えて食べてしまったり、ひも状になったプラに絡まって泳げなくなって死亡したりすることもある。
スーパーの衛生品コーナーで①と②の商品を見て回った。①のタンポンにはほぼ全てマークがついていた。ついていなかったのはオーガニックコットン製のもの。アプリケーターまでオーガニックコットン製であれば、アプリケーター付き商品でもマークはついていなかった。生理用ナプキンでは、オーガニックコットンであるなしに関わらず小型・薄型の商品全てについていたが、普通サイズのナプキンにはついていなかった。②のウェットティッシュ類では、赤ちゃんや大人の身体を拭くための各種ワイプやウェットティッシュ、掃除用ウェットシートなどにマークが付いていた。コットンなど天然植物素材を100%使ったものやオーガニックコットン認証があるものには、マークが付いていないものもある。しかし、マークのあるなしをよく確かめて商品を選んでいる人は、筆者が観察する限り認められなかった。
フランスでも美術館など公的な場所では、トイレ詰まりを防ぐため、「トイレットペーパー以外はトイレに流してはいけない」ことが強調されているので、普段からトイレに異物を流さないことを心がけている人は多いはずだ。このマークで気づくことがあるとすれば、普段あまりこのようなマークで見ることのない亀のイラストが描かれていることだろう。それは、プラが使われていると思われていない製品にも実はプラが使われており、それが海の生態系にダメージを与えてしまうことを消費者に理解してもらう啓蒙的な意味がある。例えば、不織布でできているウェットティッシュは、形状が紙に似ているので、原料にポリエステルなどの合成繊維が使われていることに気づかない人も多いだろう。生理用品もまた紙製品のように思えるが、吸収性を高めるなどの目的で多くの合成樹脂や合成繊維が使われている。こうしたものがトイレに流されてしまえば、含まれたプラ部分は下水処理で細かくなってマイクロプラになる。それが海に流れることで海洋汚染の原因になるのだ。トイレに捨てなければ、少なくとも水の中でマイクロプラになることは防ぐことができる。
買い物客の様子を見る限り、「Plastic in Product」ロゴマークの認知は不十分。たとえ亀のイラストの有無に気付いても、素材や成分にプラが使われていることを理解しない限り、その意味するところを納得して選ぶことは難しい。果たしてこの亀のイラストは生活者のリテラシー向上やエシカル消費を促進するのだろうか。実際の効果が生まれるにはまだ時間がかかりそうだ。★
■羽生のり子
1991年から在仏。文化、美術、環境問題、農業、食、フランス社会について執筆するフリージャーナリスト兼ヨガ教師。環境記者協会、自然とエコロジーの記者作家協会(いずれもフランス)会員。共著に「新型コロナ 19氏の意見 われわれはどこにいて、どこへ向かうのか」(農文協 2020)
月刊『国際商業』2024年03月号掲載
トップ画像著作者:rorozoa/出典:Freepik